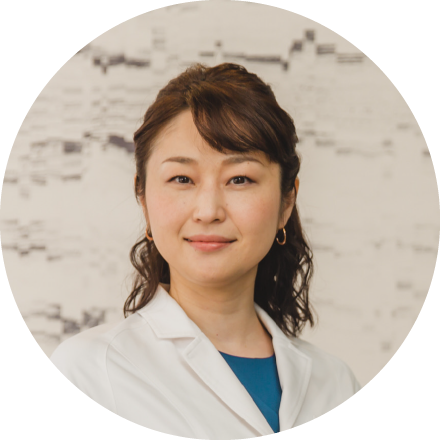
工藤紀子
小児科専門医・医学博士



今回のテーマは、「便秘」。新学期や新生活がスタートする春は、環境の変化から便秘になる人が増える時期です。
まず、便秘とはどんな状態を指すかというと、以下の定義があります。
便秘の定義

最後の「漏れていることがある」というのは、大腸は水分を吸収する役割があり、便は排出されないとどんどん硬くなっていきます。大きな塊が居座っているのに、便は次々とできていくので、塊の横をすり抜けて漏れるという現象が起こるのです。たまに「小学生の子どもの下着がいつも汚れている。発達的に問題があるのでしょうか?」と相談されることがあるのですが、診察してみると実はひどい便秘で、便秘が解消されると下着が汚れる現象も解消されるということをよく経験します。
では快便はどんな状態を指すのかというと、「毎日、もしくは1日おきに出る」という状態です。便意を感じた後、ちょっといきんでスルッと出るくらい。トイレに入って5分以内に出るのがよく、理想は1~2分。お尻を拭いた時に血がつかない状態です。
いい便の硬さの目安は、歯磨き粉やハンバーグの種、熟したバナナくらい。きっとみなさんが想像されているよりも、軟らかめだと思います。

便秘はよくあること、たいしたことはないと思って放置していると、悪循環に陥り、ますます便が出なくなってしまいます。
便秘は大きく分けると2タイプがあります。
1つ目「硬くて出せないタイプ」。便が溜まっていくと大腸で水分が吸収されて硬くなり、排便時に痛みを伴う。
すると排便は痛いと脳が理解してしまい、便意を感じるのに痛いからと我慢するようになり、さらに硬くなって…という悪循環が起きてしまいます。
便秘の悪循環のメカニズム

2つ目は「どっさり溜め込むタイプ」。便が溜まって大きな塊になると、腸が伸びていきます。便がある程度の塊になると、腸は「そろそろ出してもいいよ」と脳に信号を送るのですが、我慢しすぎていると溜め込む癖がつき、大きな便が溜まってようやく信号が送られるという悪循環に陥ります。
「硬くて出せないタイプ」には、内服薬を用いて便をやわらかくする治療を行い、排便の恐怖心を取り除いていきます。「どっさり溜め込むタイプ」に対しては、内服薬や座薬、浣腸などでお腹を動かして便を出し、本来出すべき便の量ができたら出る治療を行います。
便秘の治療はクセになって良くないのでは? と不安になるかもしれませんが、その点については大丈夫。薬がクセになることはありません。きちんとしっかり治療して「便秘でない状態」を続けていれば、薬は減らせるし便秘もよくなります。便秘の治療には時間がかかるものです。また、便秘状態の7割の方がイライラする、気分が優れないというアンケート結果が出ています。気持ちの部分に影響するものなので、便秘状態は改善させましょう。
もし、以下のような症状がある場合は受診をおすすめします。
受診を検討すべき症状

子どもが小学生以上になってしまうと、ひとりで排便もできるため、どんな便をしているのか親が把握しなくなります。便は健康状態のバロメーター。汚いとか隠さなきゃいけない事ではなく、生理現象で、身体の変化を知らせてくれるものです。普段から自然と話題にすることで、子どもが不安を感じた時に安心して話せる環境をつくることが大切だと思っています。

便秘状態を改善して、快便になるための方法を2つご紹介します。
1つ目は食事です。食物繊維は腸内環境を整える働きがあり、便秘の改善に欠かせませんが、日本人は圧倒的に足りていません。2歳までは1日5g、2歳以上は年齢プラス3~5gを目安に摂りましょう。成人の食物繊維の1日あたりの摂取目標は、男性で22g以上、女性で18g以上とされています。
私が食事で常々大切にしているのは毎日続けられて、大変ではないこと。苦にならないことです。便秘になったからといって特定の食品を大量に食べても効果はほとんどありません。そこでおすすめしたいのが、毎日の主食を変えること。ごはんの白米を雑穀ご飯に変える、パンは全粒粉やライ麦など、茶色い色のものを選ぶといいです。
2つ目は姿勢です。排便をするときの姿勢は相撲の力士が「はっけよい」と、取り組みを始める時に腰を低くするポーズがいいと言われています。トイレが和式から洋式化したことで、ぐっと座り込む姿勢が苦手な人が増えています。腰に優しい、節水効果があるなど良い面もありますが、実は和式トイレは排泄に適した姿勢を作ってくれるものだったのです。

洋式トイレで「はっけよい」にするは、足元に台を置いて利用するのがおすすめです。私たちは排便時、お腹に力を入れて腹圧をかけながら、おしりの筋肉は緩めるという高度なことをやっているのですが、子どもはもちろん、大人でも背が低いと足がしっかりと床につかなかったり、ついてもいきみにくい姿勢だったりして、なかなか難しいものです。台を置き、膝が少し曲がるくらいの態勢にすると「はっけよい」の姿勢になり、いきみやすくなります。
次回はさらに便秘を改善するために、腸内環境にフォーカス。糀や味噌など発酵食品と腸の関係性についてお話します。
新学期、新年度、新生活がスタートする時期は便秘になりやすいもの。食事と姿勢に気をつけて、便秘を予防しましょう!
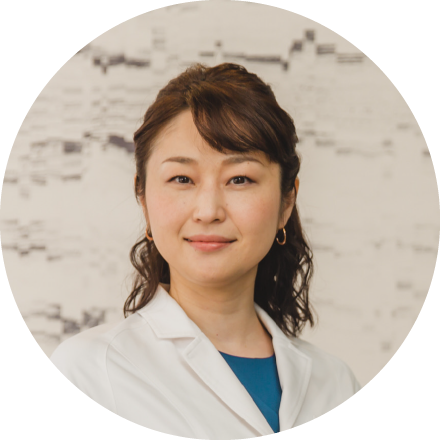
工藤紀子
小児科専門医・医学博士
プロフィール
順天堂大学医学部卒業、同大学大学院小児科思春期科博士課程修了。栄養と子どもの発達に関連する研究で博士号を取得。日本小児科学会認定小児科専門医/日本医師会認定産業医/日本医師会認定健康スポーツ医/保育園、幼稚園、小中学校の嘱託医を務める/現在2児の母。クリニックにて、年間のべ1万人の子どもを診察しながら子育て中の家族に向けて育児のアドバイスを行っている。