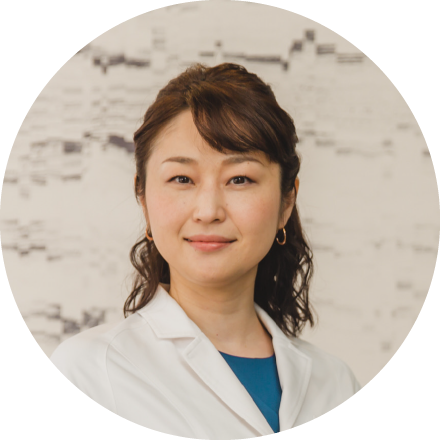
工藤紀子
小児科専門医・医学博士



今回のテーマは「熱中症」。最近は5月や6月でも真夏のような暑さを感じる日がありますね。夏本番を迎える前に、熱中症についてしっかり知っておきましょう。
私たちの体は、暑さを感じると汗をかいたり、皮膚から熱を放出したりして体温を調節します。でも、気温や湿度が高いと汗が蒸発しにくく、体の熱がうまく逃げません。さらに汗をかくことで体内の水分と塩分が失われ、血液の循環も悪くなってしまいます。すると体温がどんどん上がり、熱中症を引き起こしてしまうのです。
I度(軽症):立ちくらみ、ぼーっとする、筋肉のけいれん(足がつる)など。軽度の塩分不足で起こる症状です。
II度(中等症):頭痛、吐き気、強いだるさ、力が入らないなど。救急外来を受診するケースの多くはこの段階です。夏休みに子どもとプールに行ったお父さんが、ふらふらになって来院されることもあります。
III度(重症):高熱、けいれん、意識障害など。体温が40℃を超えると命にかかわる危険な状態で、すぐに救急車を呼ぶ必要があります。体の熱を調節する機能が完全に崩れた「オーバーヒート状態」とも言えるでしょう。

熱中症には、大きく3つの原因があります。
1. 環境要因
高温・多湿、風が弱い、直射日光が強い、締め切った室内、エアコンがない部屋など。急に暑くなった日も、体がまだ暑さに慣れていないため要注意です。
2. 体の要因
高齢者、乳幼児、肥満のある方、持病のある方、栄養状態が悪い方など。また、寝不足や二日酔いなど体調不良もリスクになります。
3. 行動の要因
運動や屋外作業で体を激しく動かしたり、夢中になって水分補給を忘れてしまったりするケースです。たとえば野球、サッカー、屋根の修理など。
この3つの要因が重なることで、熱中症は起こりやすくなります。

体調がおかしいと感じたら、すぐに涼しい場所へ移動し、安静にしましょう。できれば足を少し高くして寝かせ、体を冷やします。経口補水液を摂るのが理想ですが、なければスポーツドリンクでもOKです。
意識がもうろうとしているときは、ひとりにせず、必ず誰かがそばにいるようにしましょう。
ペットボトルを渡して、自分で開けて飲めるかどうかを確認するのも、意識や筋力の状態を見極める方法のひとつです。
もし、意識障害やけいれん、高熱が続く場合は、すぐに救急車を呼びましょう。ホースやバケツがあれば、水をたっぷりかけて体を冷やしてください。

暑い日の屋外活動では、日よけや送風機を使うなど、熱をこもらせない工夫が大切です。そして、こまめな水分・塩分補給が何より重要。汗で失うのは水分だけではなく塩分(ナトリウムなど)も含まれるため、水だけでは不十分です。
おすすめは、経口補水液やスポーツドリンクの活用。水を飲むときには、塩むすびなどを一緒に摂るのも良い方法です。糖と塩分が同時に補えます。
運動や作業の前には250〜500mlの水分を、作業中は15〜30分ごとにコップ1杯程度の水分を摂取しましょう。プロの運動選手も、運動前後の体重を測って失われた水分を補っています。
また、暑い日は湿度が高いと喉の渇きに気づきにくくなるため、「喉が渇く前に飲む」ことが大切です。とくに子どもは夢中で遊んでいると水分補給を忘れてしまうので、大人が声をかけてあげましょう。スマホなどのタイマーを使っても良いですね。
さらに、前日からこまめに水分を摂っておくと、熱中症の予防効果が高まります。運動会やレジャーなど、暑さが予想される日の前日から準備しましょう。
最近は、手を冷やすことによる体温調節も注目されています。手には体温調節に関わる血管が集まっており、15℃前後の冷水に手を浸すことで、効率的に体温を下げることができます。冷たいペットボトルを握ったり、水道水で手を冷やしたりするのも効果的です。

子どもは、大人に比べて体温調節の機能が未熟で、汗腺の発達も不十分です。さらに、身長が低いために地面からの熱の影響も受けやすく、体温が上がりやすいのです。
そのため、衣・食・住の工夫が欠かせません。
・衣類の工夫
おむつをしていると熱がこもりやすいため、少し薄着を心がけましょう。基本的には大人より1枚少なめが目安です。
ロンパースはお腹が出ずに便利ですが、体にぴったりしているため熱がこもりやすい場合も。夏は風通しのよいゆったりした服がおすすめ。女の子ならワンピース、男の子ならTシャツ+短パンなどが良いでしょう。
・食事・水分管理
子どもは自分から水分補給をしにくいため、大人が15~20分おきに声をかけて飲ませる工夫を。先ほどと同様にタイマーを使って時間管理するのも効果的です。
・室内環境の工夫
冷房は室温を25〜28℃程度、最近は猛暑日になることもあるので難しい時もありますが、外気温との差は7℃以内を目安に。湿度は40~60%を維持できるようにしましょう。温度だけでなく湿度も体感温度に大きく影響するため、温湿度計を設置するのがおすすめです。

そして、子どもも大人も大切なのが「暑熱順化(しょねつじゅんか)」。
暑くなる前から少しずつ外で体を動かし、体を暑さに慣らしておくことが、熱中症を防ぐ第一歩です。6月の過ごし方が、夏の健康を左右すると言ってもいいでしょう。
熱中症は、正しい知識と予防策でほとんど防ぐことができます。夏本番に備えて、今からできる対策を始めましょう。
次回は「夏バテ対策」についてお届けします。どうぞお楽しみに!
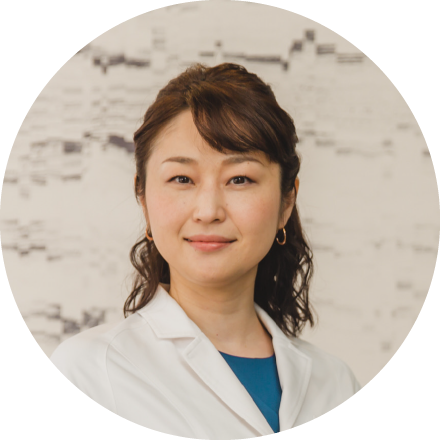
工藤紀子
小児科専門医・医学博士
プロフィール
順天堂大学医学部卒業、同大学大学院小児科思春期科博士課程修了。栄養と子どもの発達に関連する研究で博士号を取得。日本小児科学会認定小児科専門医/日本医師会認定産業医/日本医師会認定健康スポーツ医/保育園、幼稚園、小中学校の嘱託医を務める/現在2児の母。クリニックにて、年間のべ1万人の子どもを診察しながら子育て中の家族に向けて育児のアドバイスを行っている。