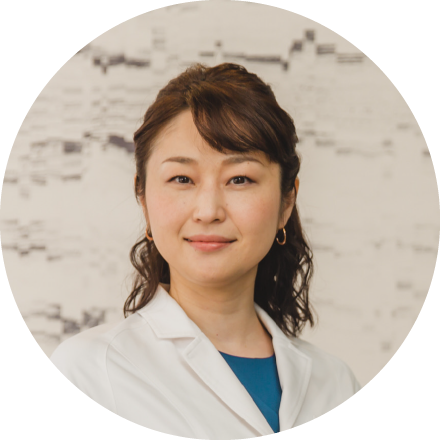
工藤紀子
小児科専門医・医学博士



前回のテーマの熱中症とも関連が深い“夏バテ”について紹介します。夏バテは、医学的な病名ではありませんが、体がだるくなったり、疲れやすかったり、食欲が出ないなど、いわゆる夏に起こる不調を指します。その主な原因は、外と室内の気温差に体が対応しきれず、体温のコントロールがうまくできていないことにあります。暑いと屋外での活動を控えるため、運動不足になったり、睡眠不足・質の良い睡眠が得られず何度も起きてしまったりするのも夏バテの原因と考えられます。
夏バテにならないためには、熱中症対策でもお話しした「暑熱順化」が大切です。これは、暑さに体を少しずつ慣らして、汗をかきやすい体を作っていくことを意味します。湿度が高いと汗をかいて脱水状態になっていることに気づきにくく、喉が渇いたと感じていなくても、こまめに水分を摂取することが重要です。

夜、眠る時にエアコンをつけたくないという方もいますが、私たちは涼しい環境の方がよく眠れる傾向にあります。暑くて汗をかきながら眠ろうとしても、いい睡眠は得られません。適切にエアコンを使いましょう。温度だけでなく、湿度をコントロールするとより涼しく感じられます。湿度計も利用して、温度は25−28度、湿度は40−60%を目安に、快適な環境で睡眠を取りましょう。直接風が当たらないよう工夫し、日中の暑さに負けないために夜間の良い睡眠を心がけましょう。

もし夏バテになってしまった場合は、食欲が湧かなくてもしっかり3食の食事を取り、こまめに水分補給することが大切です。バランスのいい食事を心がけることはもちろん、特に意識したい栄養素はビタミンB1です。ビタミンB1は疲労回復に効果があり、お米などの炭水化物をエネルギーに変える役割を担っています。豚肉、うなぎ、大豆などの豆類に多く含まれるので、意識して摂りましょう。
ビタミンB1の働きを助けてくれるのがアリシンで、これはネギ、ニンニク、ニラなどに含まれています。「豚ニラ炒め」は夏に食べると元気になれるイメージがありますが、豚肉のビタミンB1とニラのアリシンに、タンパク質のバランスがいい卵を加えるとさらに効果的です。疲れた時は、豚ニラ卵炒めを作ってみてください。

ビタミンCやクエン酸も疲労回復に良いと言われています。ビタミンCは自分では作ることができない栄養素の一つなので、しっかりと摂ることが大切です。ビタミンCと聞くとイメージされるのがレモンですが、普段の食事にちょい足しするのがおすすめです。レモンは旨みもプラスできるので、ちょっと味が足りないなと思ったら塩ではなく、レモンを足してみてください。例えば、オイルやクリームベースのパスタにもレモンを搾ると旨みが増して美味しくなります。
特に女性の場合、体の疲れを感じる際に鉄分不足のことがあります。ビタミンCは鉄分の吸収をサポートしてくれるので、例えば鉄が豊富な赤身のお肉や豆類、野菜とビタミンCが豊富な食材を一緒に食べると吸収力が上がり、効率よく栄養を摂取できます。

暑いとそうめんやアイスクリームなど炭水化物や糖質を取りがちになりますが、栄養バランスが崩れると、さらに疲れやすくなってしまいます。そうめんを食べるなら豚しゃぶを添えたり、納豆を加えたり、ネギを多めに入れるなど工夫をしましょう。
手間がかからず食べられて、しかも栄養豊富な食べ物としては卵や牛乳があります。これらを意識して食べることも大切です。土用の丑の日にはうなぎを食べる習慣がありますが、うなぎはビタミンB1とビタミンAが豊富で、ビタミンAもビタミンB1同様、疲労回復に効果的な栄養素の一つです。昔の人たちも夏バテ対策になる食べ物を食べて、暑さを乗り切っていたのだろうなと思います。

夏は野外に出かけたり旅行したりする機会が増えると思いますが、そこで気をつけたいのが虫除け対策です。
一つは、子どもの場合、虫に刺されたところをかいてしまって「とびひ」になることが多いため、そもそも虫に刺されないようにすることが大切です。もし、とびひになってしまった場合は、しっかり洗って抗菌薬を含む薬をつけ、絆創膏やガーゼで覆いましょう。家族にうつることがあるのでタオルは分け、お風呂は最後に入るようにしましょう。もう一つは、日本脳炎などの蚊が媒介する感染症予防のためです。日本での感染報告は少ないものの、東南アジアなどの暑い地域にはまだまだ多く見られます。予防接種でリスクを減らすことができますが、海外旅行に行くときは現地の感染状況も確認し、虫除け対策も心がけましょう。

対策として医学的にエビデンスがあるのは、ディートやイカリジンという虫除け成分が入っている虫除けスプレーです。虫除けリングや虫除けシール、ハッカスプレーなどさまざまな商品もありますが、現時点で医学的な効果は証明されていません。虫除けスプレーを選ぶ際は、ディートやイカリジンが入っているか確認してみましょう。イカリジンは乳児から使うことができます。スプレー以外にもウェットシート状になっているものも便利です。
年々暑さが厳しくなってきましたが、暑さ対策をしっかりして体調が崩れないように頑張りましょう!
次回は妊婦さんにとって大切な栄養素についてお話ししたいと思います。
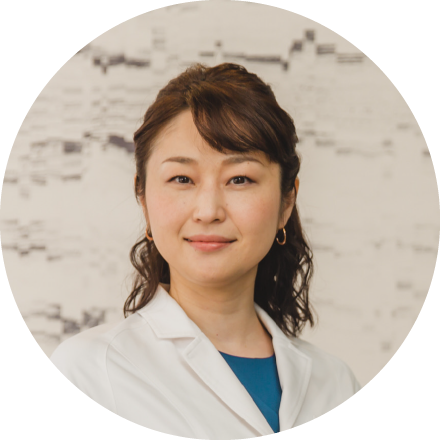
工藤紀子
小児科専門医・医学博士
プロフィール
順天堂大学医学部卒業、同大学大学院小児科思春期科博士課程修了。栄養と子どもの発達に関連する研究で博士号を取得。日本小児科学会認定小児科専門医/日本医師会認定産業医/日本医師会認定健康スポーツ医/保育園、幼稚園、小中学校の嘱託医を務める/現在2児の母。クリニックにて、年間のべ1万人の子どもを診察しながら子育て中の家族に向けて育児のアドバイスを行っている。