愛媛、食の現場へ
「石積みによって、地域の人が安心して
農業を続けていけるよう支えたい」
石積み修繕士 亀井彩香さん
2025/07/31
愛媛、食の現場へ
2025/07/31


段々畑の石積みを修繕する“石積み修繕士”として活動する女性がいる。そう聞いて興味を惹かれ、愛媛県西予市明浜町を訪れました。そこで出会った亀井彩香さんからこの土地のこと、なぜ石積みを行うことになったのか、お話を伺いました。

「見せたい風景があるので、行きませんか?」 。明浜町に住む亀井彩香さんに誘われ、連れて行ってもらったのは、この地域が見渡せる見晴らしのいい場所でした。段々畑と、そこに植えられたみかんなどの柑橘類の果樹畑、そして入り組んだリアス海岸の海が一望できます。
この土地に住む先人たちが、山の斜面を階段状にして平地にし、石積み(石垣)をつくって、崩れにくい段々畑になるよう整備したのは戦前のことだそう。見渡すと段々畑は高地まで続き、明浜町の独特の景色をつくり出しています。

「時々、昼食に持ってきたお弁当をここで食べることもあるんですよ」と話す亀井彩香さん。
「石積みは、農作業がしやすいよう畑を安定させる土台になります。また、石を積む時に、コンクリートで固めないため、水はけが良く空気が通り、土壌の性質をよく保ってくれるという特徴もあります」と亀井さん。


丁寧に石を積んでできた石積みは、300年ほど保たれると言われているそうです。しかし、場所によっては、水害やイノシシなどの動物によって崩れてしまっているところも。この地域の農家の皆さんは、自ら石積みを直すことができますが、人手不足や高齢化によって、石積みが修繕されないままになっているところがあるのです。そこで、仕事として石積み修繕をしてくれる若者に来てほしい。そうした思いで「地域おこし協力隊」の募集が行われたのが、2022年頃のことでした。

同じ頃、亀井さんは大学を卒業し就職をしますが、コロナ禍で思う通りの仕事ができず、将来に悩みを持っていました。そこで、まずは妹を頼って、住んでいた鹿児島県から愛媛県に移ります。大学の農学部で海の環境を学ぶなど自然環境に関心があったため、より自然に近いところに行きたいという思いもありました。
「そこから、明浜町に移り住むようになるまでの流れは、出会った誰か一人が欠けても実現しなかった」と亀井さん。まるで導かれるように明浜町を訪れ、その後、この町の住人になります。
「最初にここにやってきたのは、2021年。みかん収穫のアルバイトをするためでした。その時、泊めてもらった家で、石積みのことを教えてもらったんです」。面白そう!と思った亀井さんは、翌年開催された、石積み修繕のためのワークショップに参加するために、明浜町に再び訪れます。そこで石積みを体験。石積みのゲーム的な楽しさに“どハマり”し、「地域おこし協力隊」として、この土地に移住を決めたのでした。

町ではみかんをはじめ、30種類以上の柑橘類が栽培されている。
「そもそも石積みに正解はありません。積む人によって、見た目も強度も違う。お城などの石垣と違い、農地は早く効率的に積むことが大切ですが、正解は一つではありません。それが私の性格にあっていたのかもしれませんね」
また、石積みはチームで行うところに面白さがあると言います。
「例えば、数メートル幅の石積みを直すにも、石を運んで土を上げてと、大変な労力がかかります。でも、3〜4人いれば、上段と下段に分かれて、土を渡す人、受ける人、積みやすい石がどれかを考えて前に寄せる人など、チームで連携して石を積んでいくことができます。誰がどの役割を担うのか、適材適所もあって、例えば、力の強いお父さんと華奢なお母さん、小学生の子どもというチームでも、それぞれにあった役割を担ってうまく連携すれば、きれいな石積みを素早くつくることができます。石積みは、誰にでもできるとよく言われるのですが、そこが魅力のひとつでもありますね。また、石を積みながら、チームでコミュニケーションが生まれるのも楽しいところです」

亀井さんが、この土地への移住を決めたのは、石積みに魅せられたからだけではありません。この土地の人々の温かさが、何より決め手になったそうです。
「本当にここの土地の人は優しいんです。ちょっとおせっかいとも言えるかもしれません(笑)。すぐに家においでって、ごはんを食べさせてくれたり、最初からとても優しくしてくれて。当時、自分の将来に迷っていた私が、ここに来てお世話になった人たちの役に立つ仕事がしたいと思ったのも、移住を決めた大きな理由のひとつです」

地域おこし協力隊は、通常3年を期限とする制度です。しかし、亀井さんは来た当初から、3年後に町を離れるイメージは持っていなかったと言います。
「今思うと不思議ですが、ずっと住むんだろうなと最初から感じていました。山と海が近いこの土地が大好きだから、石積みを仕事にすれば、ずっとここに住んでいられるなと思ったんです」
そうして、土地と人に惹かれて石積みを行っていると、当初の「面白い、楽しい」という感覚だけでなく、石積みを通してこの地域のすごさが分かりはじめたそうです。
「例えば、石積みをする際、積んだ石の後ろに“裏込め石(ぐり石)”と呼ばれる詰め物をする必要があるんです。それによって石積みが崩れにくくなったり、ガタガタしたところが安定したりします。当初、石積みを始めたばかりのころは、裏込め石が入っていないところを見ると、『昔の人も結構適当にやってたんだなぁ』なんて思っていたんです。でも、徐々にこの土地を知るようになってからは、『裏込め石を入れなくてもいいから、とにかく早く土を固めて平地をつくり、作物を植えようと頑張っていたんだな』と、その時代の苦労に思いを馳せることができるようになりました。また町中にあるこの石積みを眺めて、この量の石を運んでくることがどれほど大変だったのか、リアルに想像できるようになったんです」

さらに、亀井さんはこう続けます。
「ここにある石積みは、一つ一つ、誰かが石を積んでできています。積んだのは、私のような女性だったかもしれないし、子どもだったかもしれません。この土地の石積みに使われる石の大きさは、ちょうど女性でも持ちやすい大きさになっているので、そんな風に想像が広がります。石積みを通して、当時の人々と交流しているような気持ちになるんです。そうして、昔の人の暮らしや頑張りに思いを馳せるようになって、より一層、昔の人の働きや土地に敬意を払う気持ちが生まれました。また、石積みを用いて農業をする様子は、愛媛の他の地域でも度々見られるので、その土地その土地の歴史なども、もっと知りたいと思うようになりました」

今ではこの土地のみかん農家の男性と結婚し、1児の母となった亀井さん。石積みをどのように広め残していくのか、夢は広がります。
「その昔、頑張って土地を整備した人がいるからこそ、今この土地の農作業がとてもやりやすいんです。少し離れた地域では、段々畑が少なく、ほとんどの果樹を山の斜面で育てているところもありますが、それはとても大変な作業です。
段々畑とそれを支える石積みはこの土地の人にとっては財産。だからこそ、修繕できる人がこれからもい続けることがとても大切です」と亀井さんは言います。
しかし、今石積みを修繕する人は少なく、亀井さんたちだけでは、手が回っていないのが現状です。さらに、石積み修繕士を職業にする人を育てるのも現実的ではありません。
「頑丈な石積みは300年持つと言われています。丈夫な石積みを築くほど、次の世代の石積みの機会が減り、積み直す技術を受け継ぎにくいという側面がありました。だからこそ、専門の職人ではなく誰もがちょっとした知恵として、石積みができることが大切だと私は思っています。まるで家庭でつくる味噌のように、石積みが代々受け継がれる技術のようになっていったら。崩れたら修繕できる人が日本中にもっともっと増えたら、この土地はもちろん、各地の石積みをいつまでも守ることができると思うんです」

そのため、亀井さんは、ワークショップを開くなど、レジャーとして石積みを広めています。
「県外から参加者が来て、石積みをしながら、『この大きい石、置きづらかったよね』と話していたり、家族みんなで石積みを体験して楽しそうにしている姿を見ると、本当にうれしい気持ちになりますね。石積みは残るものですから、家族や仲間と積んだ石積みが記念にもなってくれると思います」
こうして石積みを体験する仲間を増やしながら、これからの明浜町のこと、そして石積みのことを考えていきたいと亀井さん。

「さまざまな人にこの土地を訪れてもらい、土地の歴史や風土に触れる体験をすると同時に、楽しみながら石積みを体験し修繕してもらう。そんな機会を増やして、仕組み化することができたらと考えています。そうして、この土地の人が安心して農業を続けていけるよう支えていきたい。そのためにもっと頑張りたいですし、できること、やりたいことはまだまだあります」
そう語る亀井さんを、燦々と降り注ぐ太陽がきらきらと照らしていました。
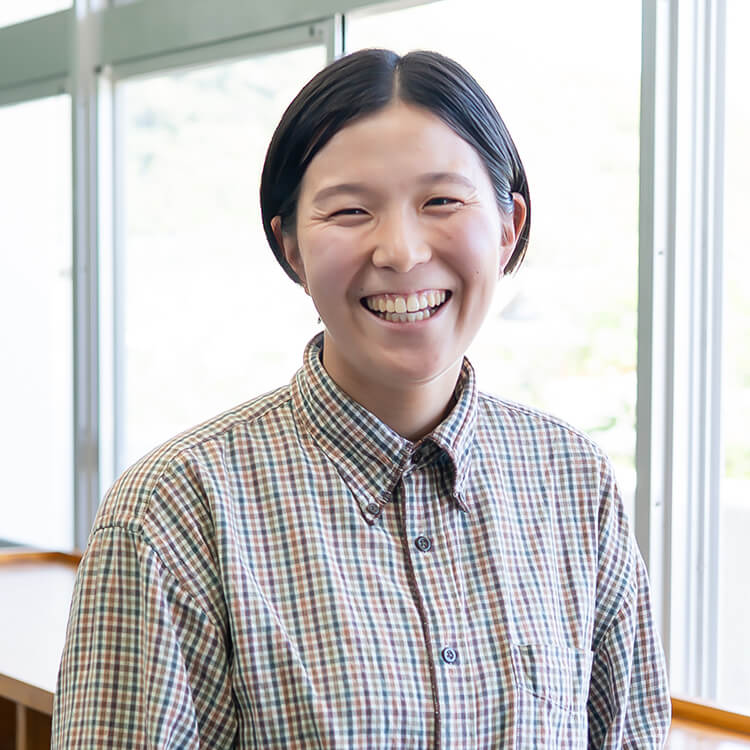
石積み修繕士
石積み修繕士
2022年に地域おこし協力隊として愛媛県 西予市 明浜町 狩江地区に移住。
地域の段々畑の修繕などを行いながら、石積みワークショップを開催するなど、石積みを広める活動を行っている。